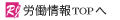▼プロローグ▼
3・11東日本大震災は、遠い沖縄にも衝撃を与えた。映像で知る大地震と大津波のすさまじさ、人災の原発事故も加わって、三重苦を背負った被災地の惨状に、胸のつぶれる思いをした。
一方で、シマクトゥバ(島ことば)の研究・伝達者、儀間進さんの言うように「東北の人は心が強い」ことに感動した。絶望や深い悲しみの中、とつとつとした語り口でしっかりと、冷静に今の自分を伝える。あのことばの力。
北国の人は辛抱強い。しかし理不尽なことには激しく怒り、納得できないことははっきりと拒絶するのを見た。再生に立ち上がろうとする意志の力にも圧倒された。高齢者、壮年、若い人たちが、自分のことばで聞く人見る人を納得させ、引きこんで、心底から一緒に悲しんだり、怒ったり、張り切ったりさせる。ほんとに強い。
ひるがえって、ウチナーンチュはああはいかないなあ──と思う。「琉球処分」による日本化で、私たちは自分本来のことばを失ってしまった。戦争体験であれ、基地に対する怒りであれ、巧言令色と恫喝を使い分けて安保体制の負担を押し付ける政府への憤りや悔しさであれ、ことばの力で他の共感を得るほど的確に伝えきったであろうか。
農村のお年寄りに、いきなり「あの米軍ヘリの飛ぶ音をどう思いますか」と聞いてごらんなさい。「はあもう、やがましいさあ」投げるように言っておしまいのはずである。戦争体験があり、戦後の苦労を経て、今爆音の下で暮らす、複雑な心情をヤマトグチ(「標準語」)でうまく表現できない。万感の思いをワンフレーズで答えてしまう。
沖縄の抗議集会や県民大会に、子どもや家族連れが何万人、何千人と参集するのは、多くの人が言い表し難い、口に出すとどこか真意と違ってしまう思いを抱え込んでいるからと思う。発言するリーダー格の人々も、そのことばは冷淡な第三者から「ステレオタイプ」と批判されることがある。それでも沖縄県民は行動で自らの意思を伝えてきた。
一九九〇年、自民党政府の「本土との格差是正」策に沿って振興開発事業を三期一二年にわたって進めた西銘順治知事(一九七八年初当選)を破り、大田昌秀革新知事が誕生した。
西銘県政が経済振興に力を入れる一方、日の丸掲揚・君が代斉唱を学校に強要し「ヤマトンチュに負けるな」主義を推進している間に、沖縄は分断されていた。全国の人々は、安保体制の負担を沖縄にしわ寄せしていることを忘れ去っていた。
だが、沖縄県民は安住するわけにはいかなかった。復帰後も、女性への性暴力・殺人・強盗など凶悪犯罪をはじめ、基地から派生する事件事故は絶えず、軍用機の騒音も激しく、生活を脅かされる問題が日常的に発生、県議会や市町村議会の抗議決議、行政の米軍や政府への抗議も聞き流される状態だったのである。
大田知事は平和・人権・女性政策を掲げて、県政の流れを変え、九四年二期目に入った。だが、基地をめぐっては、すべて日米政府の厚い壁に阻まれていた。
九五年二月、米国は、東アジアでの一〇万人の前方展開維持を確定(国防総省「アジア・太平洋戦略報告」)、日米政府による安保の再定義、軍事同盟強化が日程に上った。冷戦崩壊後、米国の海外基地が縮小されるなか、沖縄はなお基地が固定されると危惧された。
そんななか、九五年九月四日、米兵三人による一二歳の少女に対する性暴力事件が起こった。沖縄中が憤激した。連日女性たちが先導した抗議行動が繰り広げられ、一〇月二一日には、歴史に残る超党派の「少女暴行事件を糾弾し、地位協定見直しを求める県民総決起大会」が開かれた。言い難い思いを抱える市民をはじめ、各分野各層の八万五千人が結集した。復帰後初めてのことである。戦後五〇年、鬱積していた県民の怒りの爆発は、日米政府を揺るがした。
大会で「行政の責任者として少女の尊厳を守れなかったことを謝りたい」とあいさつした大田知事は、九七年三月に使用期限切れとなる米軍用地の契約更新をしない地主(未契約地主)の土地強制使用代行を拒否した。すでに飛行場となっている土地が、契約なしでは使えなくなる。二〇一五年をメドに全基地を返還させる「基地返還アクションプログラム」、返還後の中部一体を国際都市とする「国際都市構想」を立案した。初めて基地からの脱却による県づくりの青写真を描いたのである。
県内の研究者・有識者を糾合した「大学人の会」が、国を相手に、平和な生活の保証を求める違憲訴訟を提起。連合沖縄は県民投票を提唱し、「米軍基地の整理・縮小と地位協定の見直しに賛成」票が全有権者の過半数を占める結果を出した。
大田知事の軍用地強制使用のための代理署名拒否は、首相による職務命令執行訴訟に発展、違憲訴訟とともに、法廷で、沖縄が米軍基地使用の不当性を主張する機会となった。
県全体が、脱基地に向かって走り出した観があった。県議会、地方自治体・議会代表の公式訪米要請団や「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」など市民団体が米国の官民さまざまな人々に沖縄県民の意思を伝えた。
もう沖縄の基地アレルギーは治まったとばかり思っていた県外海外の人々、県内在住の政治学者でさえ、県民の本音を知って驚いた。本土のマスコミが沖縄に呼応し、九五年秋から九六年へかけて、洪水のように沖縄情報が流れたのは、七二年復帰以来である。沖縄の脱基地運動は、安保問題から目をそらしていた人々を覚醒させたようであった。
日米政府は、九五年一一月「沖縄における施設および区域に関する特別行動委員会(SACO)」を発足させて、基地の整理・統合・縮小の協議を始めた。自民・社会・さきがけ連立政権の村山首相辞任後、首相となった橋本龍太郎自民党総裁に、懸案の普天間飛行場早期返還を要請、橋本首相とモンデール駐日大使は、九六年四月一二日、五年から七年以内の「普天間」全面返還を共同発表する。
だが、県民の喜びもつかの間、県内に代替施設を建設することを条件としていたことがのちに明らかにされた。しかも、日米首脳会談で安保の再定義が行われ、軍事同盟強化の段取りが取り決められたのだ。
九七年、日米間で普天間飛行場の代替施設を名護市の東海岸に建設することを合意(SACO合意)、橋本首相は渾身の力を込めて、大田知事と沖縄の「反基地の県民意思」攻略にかかった。違憲訴訟は敗訴、国会では圧倒的な賛成多数で軍用地強制使用の特別措置法が制定された。形勢逆転、政府は県民総決起を吸い上げると見せて、うまく操作したのである。盛り上がった本土の世論も沈静してしまった。
しかし、へこたれない名護市では、普天間代替施設という名の新基地建設反対の市民運動が市民投票を実らせて、過半数の市民が基地建設反対の意思をはっきりと示した。
橋本首相が、比嘉鉄也・名護市長に、市民を裏切って代替施設建設のための調査を容認して辞任する──という苦汁を呑ませた後、抵抗する大田知事を追い落とすところから、この物語は始まる。
一方で、シマクトゥバ(島ことば)の研究・伝達者、儀間進さんの言うように「東北の人は心が強い」ことに感動した。絶望や深い悲しみの中、とつとつとした語り口でしっかりと、冷静に今の自分を伝える。あのことばの力。
北国の人は辛抱強い。しかし理不尽なことには激しく怒り、納得できないことははっきりと拒絶するのを見た。再生に立ち上がろうとする意志の力にも圧倒された。高齢者、壮年、若い人たちが、自分のことばで聞く人見る人を納得させ、引きこんで、心底から一緒に悲しんだり、怒ったり、張り切ったりさせる。ほんとに強い。
ひるがえって、ウチナーンチュはああはいかないなあ──と思う。「琉球処分」による日本化で、私たちは自分本来のことばを失ってしまった。戦争体験であれ、基地に対する怒りであれ、巧言令色と恫喝を使い分けて安保体制の負担を押し付ける政府への憤りや悔しさであれ、ことばの力で他の共感を得るほど的確に伝えきったであろうか。
農村のお年寄りに、いきなり「あの米軍ヘリの飛ぶ音をどう思いますか」と聞いてごらんなさい。「はあもう、やがましいさあ」投げるように言っておしまいのはずである。戦争体験があり、戦後の苦労を経て、今爆音の下で暮らす、複雑な心情をヤマトグチ(「標準語」)でうまく表現できない。万感の思いをワンフレーズで答えてしまう。
沖縄の抗議集会や県民大会に、子どもや家族連れが何万人、何千人と参集するのは、多くの人が言い表し難い、口に出すとどこか真意と違ってしまう思いを抱え込んでいるからと思う。発言するリーダー格の人々も、そのことばは冷淡な第三者から「ステレオタイプ」と批判されることがある。それでも沖縄県民は行動で自らの意思を伝えてきた。
一九九〇年、自民党政府の「本土との格差是正」策に沿って振興開発事業を三期一二年にわたって進めた西銘順治知事(一九七八年初当選)を破り、大田昌秀革新知事が誕生した。
西銘県政が経済振興に力を入れる一方、日の丸掲揚・君が代斉唱を学校に強要し「ヤマトンチュに負けるな」主義を推進している間に、沖縄は分断されていた。全国の人々は、安保体制の負担を沖縄にしわ寄せしていることを忘れ去っていた。
だが、沖縄県民は安住するわけにはいかなかった。復帰後も、女性への性暴力・殺人・強盗など凶悪犯罪をはじめ、基地から派生する事件事故は絶えず、軍用機の騒音も激しく、生活を脅かされる問題が日常的に発生、県議会や市町村議会の抗議決議、行政の米軍や政府への抗議も聞き流される状態だったのである。
大田知事は平和・人権・女性政策を掲げて、県政の流れを変え、九四年二期目に入った。だが、基地をめぐっては、すべて日米政府の厚い壁に阻まれていた。
九五年二月、米国は、東アジアでの一〇万人の前方展開維持を確定(国防総省「アジア・太平洋戦略報告」)、日米政府による安保の再定義、軍事同盟強化が日程に上った。冷戦崩壊後、米国の海外基地が縮小されるなか、沖縄はなお基地が固定されると危惧された。
そんななか、九五年九月四日、米兵三人による一二歳の少女に対する性暴力事件が起こった。沖縄中が憤激した。連日女性たちが先導した抗議行動が繰り広げられ、一〇月二一日には、歴史に残る超党派の「少女暴行事件を糾弾し、地位協定見直しを求める県民総決起大会」が開かれた。言い難い思いを抱える市民をはじめ、各分野各層の八万五千人が結集した。復帰後初めてのことである。戦後五〇年、鬱積していた県民の怒りの爆発は、日米政府を揺るがした。
大会で「行政の責任者として少女の尊厳を守れなかったことを謝りたい」とあいさつした大田知事は、九七年三月に使用期限切れとなる米軍用地の契約更新をしない地主(未契約地主)の土地強制使用代行を拒否した。すでに飛行場となっている土地が、契約なしでは使えなくなる。二〇一五年をメドに全基地を返還させる「基地返還アクションプログラム」、返還後の中部一体を国際都市とする「国際都市構想」を立案した。初めて基地からの脱却による県づくりの青写真を描いたのである。
県内の研究者・有識者を糾合した「大学人の会」が、国を相手に、平和な生活の保証を求める違憲訴訟を提起。連合沖縄は県民投票を提唱し、「米軍基地の整理・縮小と地位協定の見直しに賛成」票が全有権者の過半数を占める結果を出した。
大田知事の軍用地強制使用のための代理署名拒否は、首相による職務命令執行訴訟に発展、違憲訴訟とともに、法廷で、沖縄が米軍基地使用の不当性を主張する機会となった。
県全体が、脱基地に向かって走り出した観があった。県議会、地方自治体・議会代表の公式訪米要請団や「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」など市民団体が米国の官民さまざまな人々に沖縄県民の意思を伝えた。
もう沖縄の基地アレルギーは治まったとばかり思っていた県外海外の人々、県内在住の政治学者でさえ、県民の本音を知って驚いた。本土のマスコミが沖縄に呼応し、九五年秋から九六年へかけて、洪水のように沖縄情報が流れたのは、七二年復帰以来である。沖縄の脱基地運動は、安保問題から目をそらしていた人々を覚醒させたようであった。
日米政府は、九五年一一月「沖縄における施設および区域に関する特別行動委員会(SACO)」を発足させて、基地の整理・統合・縮小の協議を始めた。自民・社会・さきがけ連立政権の村山首相辞任後、首相となった橋本龍太郎自民党総裁に、懸案の普天間飛行場早期返還を要請、橋本首相とモンデール駐日大使は、九六年四月一二日、五年から七年以内の「普天間」全面返還を共同発表する。
だが、県民の喜びもつかの間、県内に代替施設を建設することを条件としていたことがのちに明らかにされた。しかも、日米首脳会談で安保の再定義が行われ、軍事同盟強化の段取りが取り決められたのだ。
九七年、日米間で普天間飛行場の代替施設を名護市の東海岸に建設することを合意(SACO合意)、橋本首相は渾身の力を込めて、大田知事と沖縄の「反基地の県民意思」攻略にかかった。違憲訴訟は敗訴、国会では圧倒的な賛成多数で軍用地強制使用の特別措置法が制定された。形勢逆転、政府は県民総決起を吸い上げると見せて、うまく操作したのである。盛り上がった本土の世論も沈静してしまった。
しかし、へこたれない名護市では、普天間代替施設という名の新基地建設反対の市民運動が市民投票を実らせて、過半数の市民が基地建設反対の意思をはっきりと示した。
橋本首相が、比嘉鉄也・名護市長に、市民を裏切って代替施設建設のための調査を容認して辞任する──という苦汁を呑ませた後、抵抗する大田知事を追い落とすところから、この物語は始まる。